エンジニア採用がますます難しくなっている現代において、開発リソースをどう確保するかは多くの企業にとっての大きな課題です。特に、大企業からスタートアップ企業まで、限られたリソースで最大限の成果を出すための開発戦略の見直しが求められています。
そこで注目されているのが「ラボ契約」という開発委託の手法です。しかし、準委任契約やSES契約など、他の契約形態との違いが分かりにくいという声も少なくありません。
本記事では、ラボ契約の基本的な仕組みから、準委任契約(SES契約)・請負契約との違い、さらにはメリット・デメリット、導入時のプロセスまでをわかりやすく解説します。エンジニア採用にお悩みの企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
詳しくはこちら!
【自社開発企業・SIer勤務のITエンジニア採用担当者に聞く採用の実態】6割以上の方が採用目標未達
【目次】
ラボ契約とは何か?
ラボ契約とは準委任契約の1種で、外部の開発ベンダーが提供する専属の開発チーム(ラボ)を、一定期間、自社プロジェクトにアサインする契約形態です。この開発チームは、あたかも自社の内製部門の一部として機能し、柔軟な仕様変更や継続的な改善が可能となります。
特にエンジニア採用に課題を抱える大企業からスタートアップまで、外部で開発体制を構築できる手段として注目を集めています。発注側が要件や優先順位の決定権を持てるため、プロダクト志向の開発にも最適です。
ラボ契約(準委任契約)と請負契約の違い
ラボ契約と混同されやすいのが、請負契約です。ラボ契約は、準委任契約の1種であるため、請負契約との違いを理解しておくことが重要です。
| 契約形態 | 責任範囲 | 向いている開発形態 |
|---|---|---|
| ラボ契約(準委任契約) | 人月単価や期間をベースとして、仕事の遂行に責任を持つ | アジャイル開発 |
| 請負契約 | 納品物の完成に責任を持つ | ウォータフォール開発 |
作業を外注するという点はどちらもメリットとして共通していますが、請負契約は納品物に対して責任を負うため、プロジェクトの要件定義を明確にする必要があり、発注後の仕様変更などは難しいことがデメリットとして考えられます。こういったことから、ウォータフォール型での開発に向いている契約形態であると言えます。
一方で、ラボ契約は、業務に対して責任を負うため、プロジェクトの進捗により柔軟に仕様の変更も可能となるため、アジャイル開発に向いている契約形態と言えます。
請負・外注・委託の違いなどはこちら!
エンジニアに業務を外注するメリットは?注意点と探し方も解説
ラボ契約とSES契約の違い
| 契約形態 | 責任範囲 | 特徴 |
|---|---|---|
| ラボ契約 | 人月単価や期間をベースとして、仕事の遂行に責任を持つ | エンジニアは受注側の企業で開発を行う |
| SES契約 | 人月単価や期間をベースとして、仕事の遂行に責任を持つ | エンジニアは発注側の企業に常駐し開発を行う |
ラボ契約も、SES契約も準委任契約の一種となります。どちらも開発プロジェクトにおいて柔軟な人材確保を可能にする手段で、直接の指揮命令関係は生じませんが、運用方法に明確な違いがあります。
ラボ契約では、エンジニアチームはビジネスパートナー側(国内・オフショアなど)に常駐し、遠隔で開発業務を遂行します。一方、SES契約はクライアント企業のオフィスにエンジニアが常駐して開発業務を遂行します。
※各企業によって形態は異なる場合があります。
SES契約について、詳しくはこちら!
SES契約(準委任契約)とは?派遣契約との違いやSES企業を利用するメリット・デメリットを解説
ラボ開発に向いている案件とは?
ラボ型契約は、専属チームを中長期的に確保することができる柔軟な開発体制です。単発の請負契約とは異なり、継続的な改善や変化に対応できることが大きな特長です。
特に以下のような案件で、ラボ開発はその力を最大限に発揮します。
- 継続的な機能追加・改善が必要なプロダクト
SaaSやWebサービスなど、ユーザーの声をもとに定期的な機能追加が求められるケース - 要件が流動的で、仕様が固まっていないプロジェクト
アジャイル開発やプロトタイピングが前提のプロジェクト - 開発後の保守・運用も含まれる長期プロジェクト
システム全体を把握した上で品質とスピードを担保する必要がある長期のプロジェクト - MVPから拡張・スケールを目指すスタートアップ
小さく始めて大きく育てる、段階的な体制拡張が必要なプロダクト開発
※MVP(ミニマム・バイアブル・プロダクト):まず最小限の機能だけでリリースして、ユーザーの反応を見ながら改善していくという考え方
このように、ラボ契約は「プロダクトを育てる」ことに適した契約形態です。継続性・柔軟性・チーム内の密な連携が求められる案件では、請負やスポット型の契約よりも高いパフォーマンスを発揮する可能性があります。
ラボ契約のメリット
ラボ契約のメリット①:専属の開発チームを安定的に確保できる
ラボ契約では、ビジネスパートナーから提供される専属チームを一定期間確保することができるため、プロジェクトに継続的に携わる体制を構築できます。業務知識や技術的なノウハウの蓄積が進みます。これにより、仕様の伝達ミスや認識のズレが減少し、品質の高い開発が可能となります。
ラボ契約のメリット②:アジャイル開発・継続的改善に柔軟に対応できる
ラボ契約は、アジャイル開発との相性が非常に良い契約形態です。専属チームが長期間稼働することで、開発サイクルの中に継続的な改善を取り込みやすくなります。市場やユーザーのニーズに応じて、仕様の変更や機能の追加が発生しても、柔軟に対応できる体制が整っているため、スピーディかつ柔軟な開発プロセスを維持できます。
ラボ契約のメリット③:エンジニア採用や教育の負担を軽減できる
多くの企業が課題として抱えるのがエンジニアの採用難です。優秀な人材を採用し、さらに育成するには大きな時間とコストがかかります。ラボ契約では、そのプロセスをビジネスパートナー側に委ねることができるため、自社の採用担当者が抱える負担を大きく削減できます。
また、ビジネスパートナー側があらかじめ構築した教育体制やチーム内ナレッジにより、即戦力の人材がスムーズに開発に参画できることも魅力の一つです。
ラボ契約のメリット④:ナレッジが継続的に蓄積され、組織全体の技術力が向上
継続して開発を行うことで、過去の仕様や技術的背景が蓄積され、開発スピードや品質が向上していきます。このようにして培われた知見は、チームだけでなく自社の開発体制全体に良い影響を与えます。結果として、ラボ契約を通じて内製化支援にもつながり、長期的には自社内に強固な技術基盤を築くことも可能になります。
ラボ契約のメリット⑤:コスト最適化の可能性がある
ラボ契約は、オフショア開発やニアショア開発と組み合わせることで、コストパフォーマンスの高い開発体制を構築できます。たとえば、物価の安い地域の開発者と協働することで、人件費を抑えながら一定以上の品質を維持することが可能です。
単なるコスト削減ではなく、戦略的なリソース配分としての選択肢となるのが、ラボ契約の強みです。
ラボ契約のデメリット
ラボ契約のデメリット①:短期プロジェクトには向いていない
ラボ契約は基本的に中長期的なプロジェクトを前提とした契約形態です。そのため、数週間〜数ヶ月といった短期間での開発やスポット的な依頼には適していません。専属チームの立ち上げにかかる準備やオンボーディング期間を考慮すると、短期案件ではコストパフォーマンスが悪化する可能性があります。
短期間での成果が求められる場合には、SES契約や請負契約など、が適しているケースもあります。
ラボ契約のデメリット②:立ち上げ初期に工数がかかる
ラボ契約では、開発チームを一から構築するため、立ち上げ初期に「チームビルディング」「役割設計」「目的共有」などの準備工数が必要になります。とくに自社内に受け入れ体制が整っていない場合、期待通りに稼働するまでに時間がかかることもあります。
準備不足のまま稼働を開始してしまうと、要件の認識違いやスケジュールの遅延につながるリスクもあるため、導入前の計画設計が重要です。
ラボ契約のデメリット③:外部チームのマネジメント負荷が発生する
ビジネスパートナーが提供するチームとはいえ、プロジェクトマネージャーやチームリーダーによる進捗管理・品質管理など、一定の社内リソースが必要になります。
特に、オフショアでの開発の場合リモートでの連携や言語・文化の違いがある場合は、チャットツールやドキュメントルールの整備、会議体の設計といったコミュニケーションコストの増加も考慮が必要です。
ラボ契約のデメリット④:ビジネスパートナーの選定を誤ると失敗するリスクがある
ラボ契約を成功させる上で、最も重要なのがビジネスパートナーの選定です。提供する人材のスキルレベルや、プロジェクトとの相性、サポート体制の有無によって、契約の成果に大きな差が出る可能性があります。
もし、要件を満たさないベンダーと契約してしまうと、期待していた成果が出ないだけでなく、開発のやり直しやスケジュールの遅延といった深刻なトラブルにも発展しかねません。ラボ契約では信頼できるパートナー選びが成功の鍵となります。
オフショア型ラボ契約と国内型ラボ契約のメリット・デメリット
ラボ契約には、海外の開発チームを活用する「オフショア型」と、日本国内でチームを構成する「国内型」の2種類があります。どちらも専属チームによる開発体制を構築できる点は共通していますが、コストやコミュニケーション、マネジメントのしやすさなどに違いがあります。以下の比較表で、それぞれのメリット・デメリットを確認してみましょう。
| 比較項目 | オフショア型ラボ契約(海外) | 国内型ラボ契約(日本) |
|---|---|---|
| コスト | ◎ 人件費が安く、コスト削減が可能 | △ 国内水準の人件費。コスト削減効果は小さい |
| 人材確保のしやすさ | ◎ エンジニアリソースが豊富で安定供給 | △ 人材不足の影響を受けやすい。パートナーの企業規模に依存する。 |
| コミュニケーション | △ 言語や文化の壁がある(日本語不可の場合あり) | ◎ 日本語・商習慣の共有がスムーズ |
| マネジメントの難易度 | △ タイムゾーン・距離の違いで管理がやや複雑 | ◎ 同一国内で進捗・品質管理がしやすい |
| 品質管理 | △ 開発レベルは企業による。指示・レビューの工夫が必要 | ◎ 国内水準の品質。レビューもしやすい |
| 導入スピード | △ 契約準備や立ち上げにやや時間がかかる | ◎ スムーズに立ち上がりやすい |
| セキュリティ管理 | △ 国によって法律・ITセキュリティ事情が異なる | ◎ 日本の法制度に準拠して対応可能 |
| 拡張性・柔軟性 | ◎ チーム規模の調整や長期契約がしやすい | △ 大規模プロジェクトになると人材確保に限界があることも |
オフショア型と国内型、どちらが優れているというよりは、プロジェクトの性質や自社の開発体制に応じて使い分けることが重要です。たとえば「低コストで開発をスピーディーに進めたい」ならオフショア、「品質や連携を重視したい」なら国内型といったように、それぞれの特性を活かした選択を行いましょう。
採用担当者がラボ契約を成功させるためのプロセス
ラボ契約は、単に開発を外部に任せるだけの手段ではなく、中長期的な視点で成果を最大化するための戦略的な契約形態です。しかし、成功に導くためには「契約すれば終わり」ではなく、導入前から運用フェーズまでの各ステップを丁寧に設計・実行することが不可欠です。
ここでは、採用担当者がラボ契約を効果的に活用し、期待する成果を得るために押さえておくべきプロセスを5つのステップに分けて解説します。
- 目的の明確化:外部に任せたい業務範囲とゴールを具体的に設定
- 信頼できるビジネスパートナーの選定:実績・専門性・セキュリティ・契約形態を総合的に比較
- 開発体制の具体的な設計:人数・役割・開発言語・フレームワークを明確化
- 円滑なコミュニケーションの仕組み作り:定例会議・ドキュメント管理等のルールを整備
- KPIとフィードバック体制の整備:KPI設定・レビュー・フィードバックを仕組み化
ラボ契約成功のステップ①:目的の明確化
まず最初に必要なのは、ラボ契約を導入する目的の明確化です。何のために外部開発チームを導入するのか、どの業務を外注し、どの範囲を内製で維持するのかといった役割分担を明確にしておく必要があります。
このステップが不十分なまま契約を進めると、期待値のズレや成果の評価が難しくなり、プロジェクト全体が不安定になるリスクがあります。まずは、社内で合意形成を図り、開発の目的・ゴール・優先順位を明文化しましょう。
ラボ契約成功のステップ②:信頼できるビジネスパートナーの選定
ラボ契約の成果はビジネスパートナーの力量に大きく左右されます。そのため、専門領域、セキュリティ体制、開発手法、など、多角的な視点からビジネスパートナーを比較検討することが重要です。
また、見積金額だけで判断せず、実際に開発チームが稼働する際のフローや体制、リーダー人材の質など、現場に近い情報までヒアリングするようにしましょう。ビジネスパートナーの選定は、ラボ契約成功の鍵を握る最も重要なステップです。
ラボ契約成功のステップ③:開発体制の具体的な設計
次に行うべきは、開発体制の設計です。何名体制でスタートするのか、各メンバーの役割(エンジニア、QA、PMなど)はどう分担するのか、使用するプログラミング言語やフレームワーク、開発手法(アジャイル/ウォーターフォール)などをあらかじめ定義しておく必要があります。
明確な体制設計があることで、メンバー選定や立ち上げ時の意思疎通がスムーズになり、稼働後の品質や速度にも良い影響を与えます。
ラボ契約成功のステップ④:円滑なコミュニケーションの仕組み作り
チームがリモートで稼働するケースが多いため、情報共有や意思決定を円滑に行う仕組みが非常に重要です。たとえば、定例ミーティングの頻度と内容、チャットツールの使い方、ドキュメント管理のルールなどを事前に取り決めておきましょう。
こうした仕組みが整っていると、コミュニケーションの質が高まり、トラブル発生時の初動も早くなるため、安定した開発体制を維持しやすくなります。
ラボ契約成功のステップ⑤:KPIとフィードバック体制の整備
ラボ契約では、定期的なパフォーマンス評価がとても重要です。KPI(重要業績評価指標)を設定し、月次や四半期ごとのレビューを行うことで、成果を可視化しながらチームの改善につなげていく体制を整える必要があります。
また、成果だけでなく、コミュニケーションやチーム内の満足度など、定性的な側面もフィードバックとして取り入れることで、より良いパートナー関係を築くことができます。
ラボ契約はエンジニア採用戦略の重要な選択肢
エンジニア不足が深刻化する中で、ラボ契約は「エンジニア採用戦略の一部」として有効に機能します。即戦力人材の採用が困難な状況において、ラボ契約を活用することで、開発リソースを安定確保できる点が大きな魅力です。
また、外部の開発文化やナレッジが社内にも波及し、自社の技術力向上や人材育成にも貢献します。内製と外注のハイブリッドな手法として、ラボ契約は今後ますます注目されるでしょう。
まとめ
ラボ契約は、中長期的な開発体制の構築に適しています。
そのメリット・デメリットを正しく理解し、自社の採用状況や開発ニーズに応じて導入することで、コスト・品質・スピードのバランスを最適化できます。
エンジニア採用に悩む企業にとって、ラボ契約は開発力を強化するための重要なパートナー戦略となるはずです。


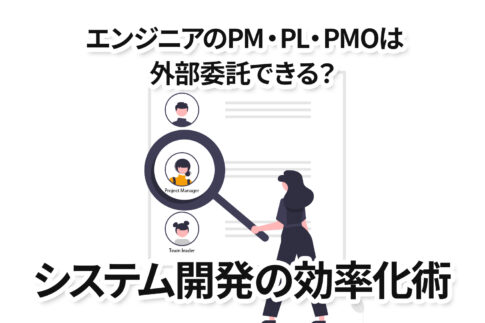

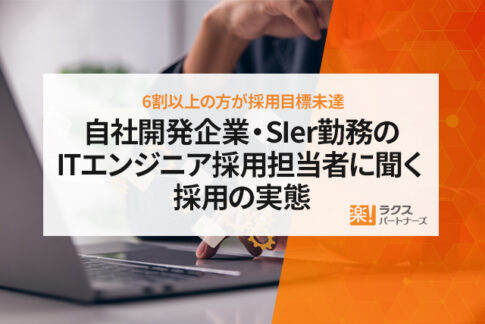

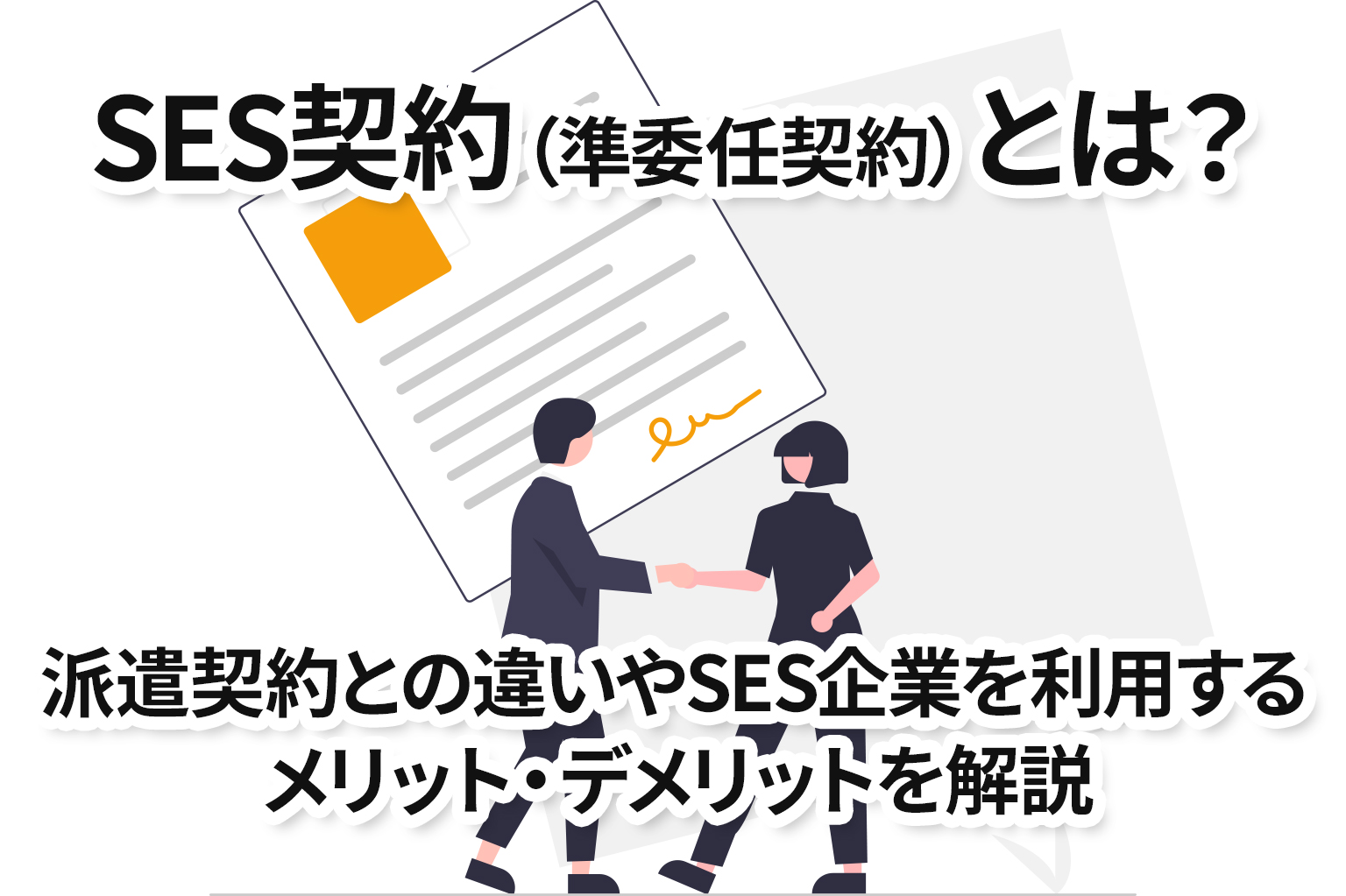


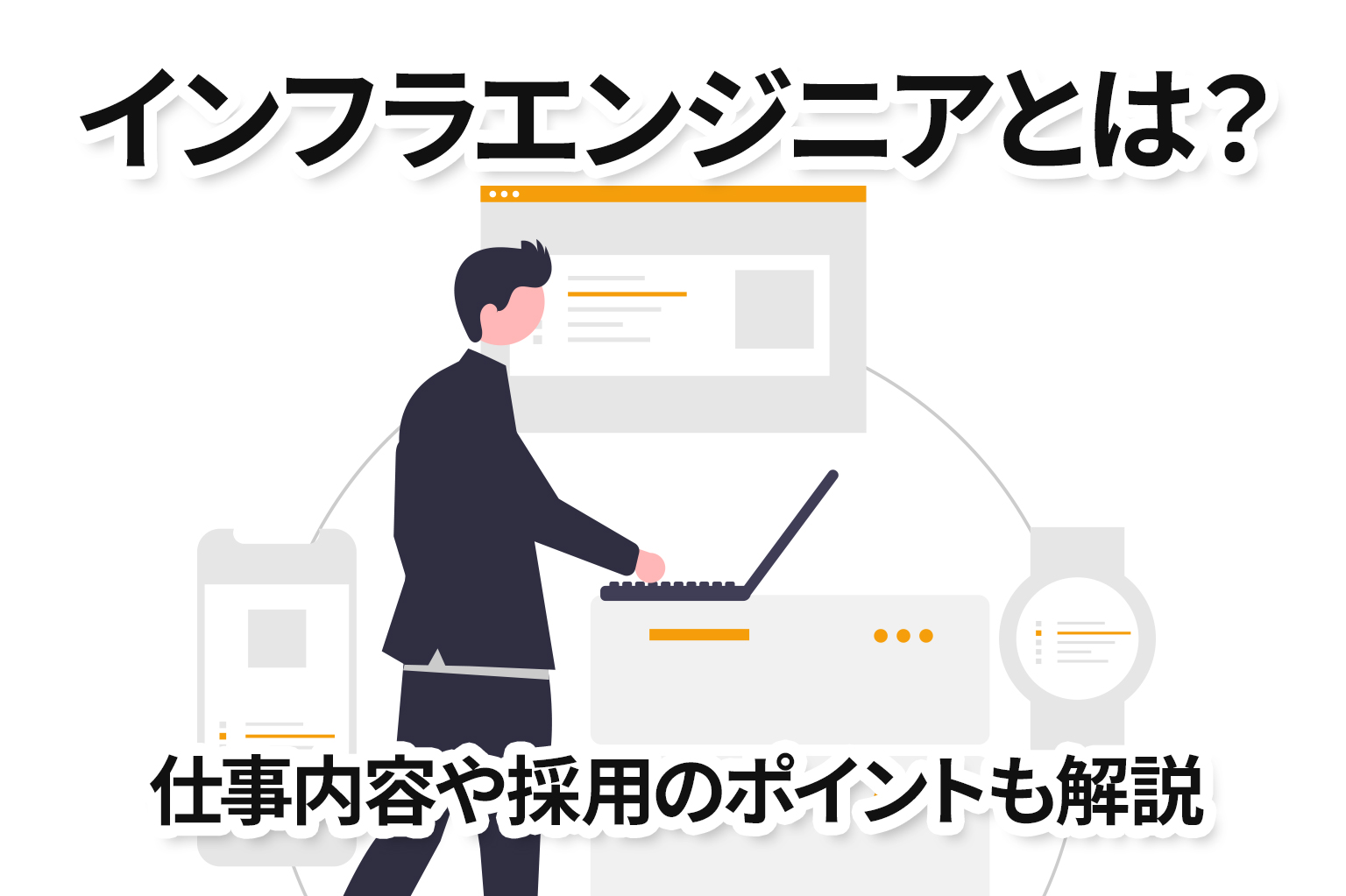
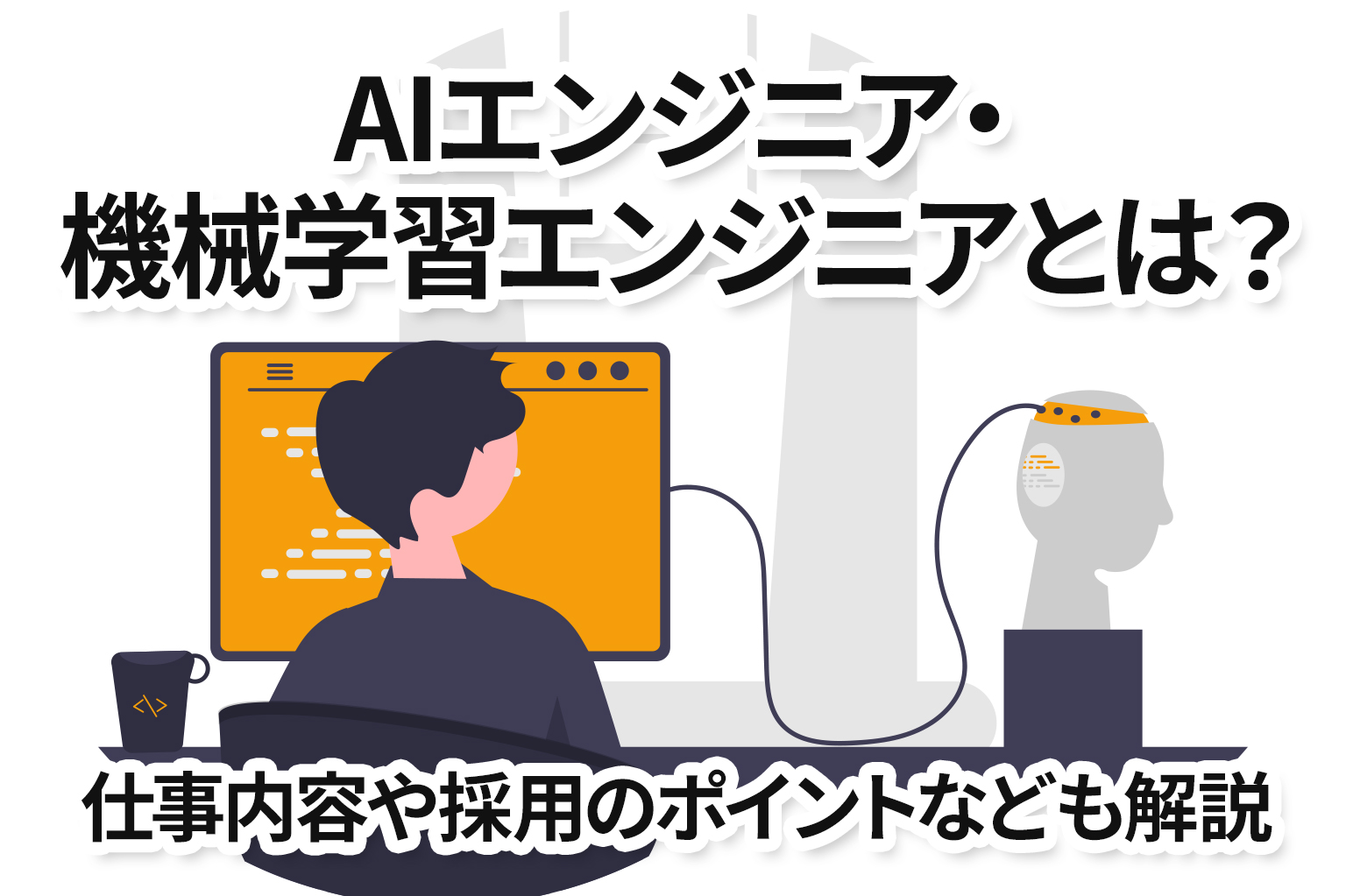

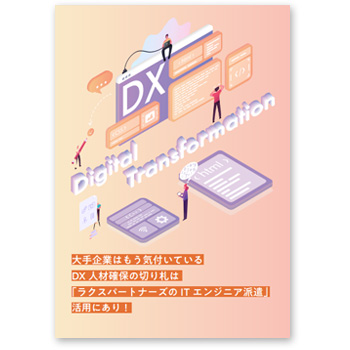
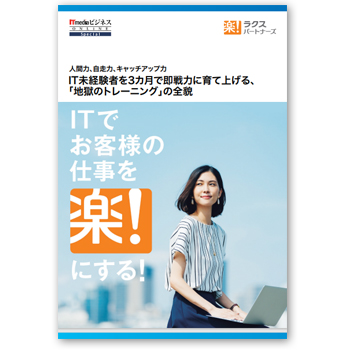
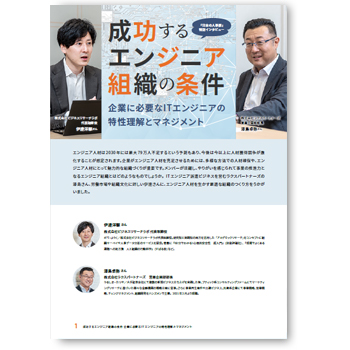
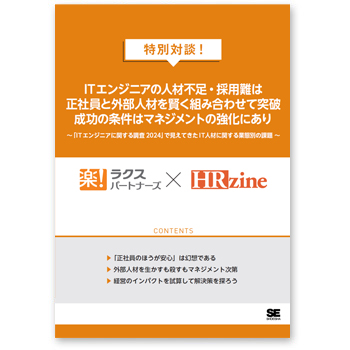
ITエンジニア採用担当者に関しての調査レポート